喜びが感じられない理由、もしかしてアンヘドニア?

こんにちは!
今回は「アンヘドニア」というちょっと聞き慣れない心の状態について、やさしく解説していきます。
なんだか、何をしても楽しくない…。
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
実はそれ、「アンヘドニア」という心のサインかもしれません。
ざっくり言うと、楽しいことをしても喜びを感じられない状態のことです。
アンヘドニア=うつ病?
たしかに、うつ病の方の多く(約75%!)に見られる症状ですが、うつ病だけに限りません。
たとえば、
- 仕事や学校でストレスがたまりすぎたとき
- 目標を見失ってしまったとき
こういうときにも、人はアンヘドニアになることがあります。
じゃあ、なぜ楽しめなくなるの?
脳の中には「ドーパミン」という、楽しいときに出る物質があります。
でも、ストレスがかかりすぎると、このドーパミンがうまく働かなくなってしまうんです。
つまり、「心の問題」だけじゃなくて、「脳の調子」も関係しているというわけですね。
SNSやゲームで気を紛らわせても意味ないの?
もちろん「ちょっと楽しい」は一時的に気をまぎらわせてくれます。
でも、根本的にアンヘドニアを乗り越えるには、もっと深いレベルでの「行動」が必要です。
気分がのらなくても、動いてみよう
「気持ちが乗ったらやる」だと、ずっと何もできないかもしれません。
でも、「ノルマみたいにとりあえずやってみる」と、だんだん気分がついてくることもあるんです。
昔好きだった趣味、軽いお出かけ、ちょっとした家事。
気合いを入れなくていいので、まず一歩、動いてみましょう。
特におすすめは運動!
ジョギング、ダンス、散歩など、週に2回くらい汗をかく運動がすごく効果的なんです。
運動すると、ドーパミンも出やすくなると言われています。
そして、人とのつながり
誰かのためにちょっと動く。
親切にする、手伝ってあげる、声をかける。
それだけで自分の気持ちも前向きになってくることがあります。
感謝の気持ちが心を守ってくれる
「ありがとう」を意識するだけでも、アンヘドニアの予防になるんです。
ハーバード大学の研究でも、感謝の習慣が心を元気にすると示されています。
というわけで
アンヘドニアは「サボり」でも「わがまま」でもありません。
脳と心の仕組みによって、誰にでも起こりうるものです。
大事なのは、気分を待たずに、先に行動してみること。
焦らず、ゆっくり、少しずつ。
あなたのペースで、また「楽しい」を取り戻せますように。



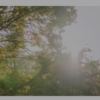
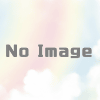


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません