知的好奇心が価値を生む時代へ
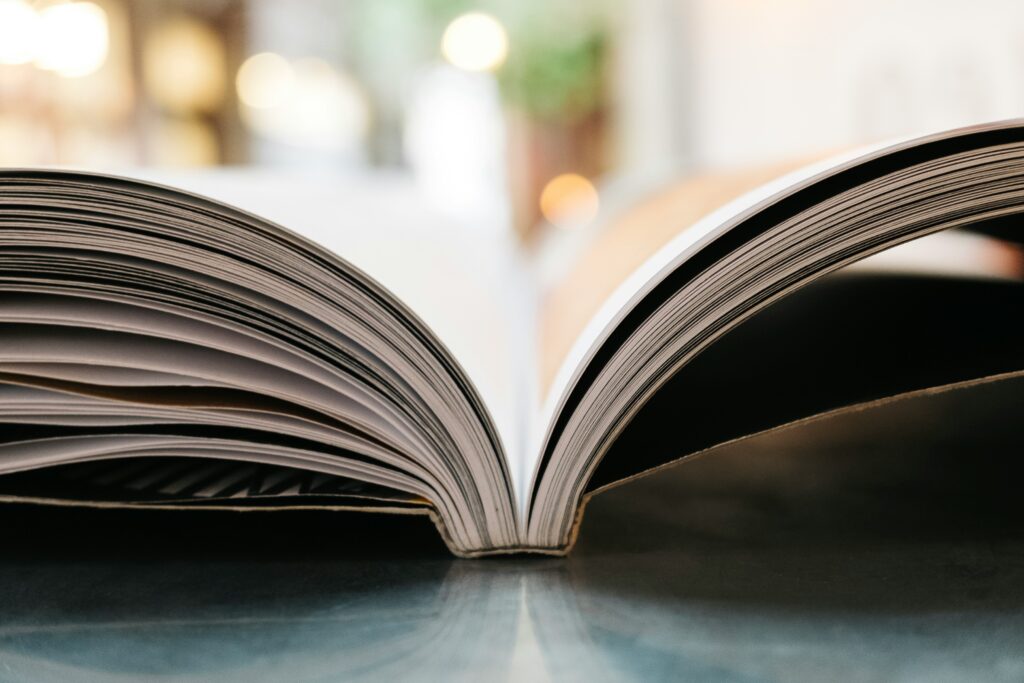
一生懸命がんばれば報われる、って本当?
日本では昔から、「まじめに努力すれば報われる」「与えられた仕事をきちんとやるのが一番大事」といった考え方が根強いですよね。
学校でも会社でも、「正解を出すこと」が評価されることが多かったと思います。
でも、ちょっと考えてみてください。
正解がはっきりしていることって、今のAIや検索エンジンの方が早く正確に処理できちゃうんです。
「与えられたことをきちんとやる」だけでは通用しない理由
例えば、「資料をまとめる」「数値を分析する」「文章を要約する」といった仕事。
これらは以前なら“人間のスキル”でしたが、今ではAIがサクッとこなしてしまいます。
つまり、「言われたことをちゃんとやる」だけでは、これからの世界では目立たなくなってしまう可能性があります。
自分の頭で考えて、「何が面白いのか」「どこにチャンスがあるのか」を探せる人が強いんです。
とはいえ、いきなり「考える力を鍛えろ」と言われても…
たしかに、「自由に考えてごらん」と言われると、かえって手が止まってしまいますよね。
でも実は、この「自分で問いを立てて、面白がれる力」って、特別な才能ではなく、日常の中で少しずつ育てていけるんです。
たとえば、
- いつもと違うルートで帰ってみる
- 普段スルーしてた広告をじっくり眺めてみる
- 興味ないと思ってたジャンルの本を読んでみる
こんな小さな「寄り道」からでも、世界の見え方がちょっとずつ変わってきます。
というわけで
これからの時代に本当に大切なのは、「知識」そのものではなく、「知識にワクワクできる力」だと思います。
誰かの指示を待つのではなく、自分で問いを見つけて、自分で動いてみる。
正解が決まっていない時代だからこそ、「面白がれる人」が一番強い。
そう思えるだけで、ちょっとだけ気持ちが軽くなりませんか?
あなたの「これってなんでだろう?」を、大事に育ててみてくださいね。
「問いを立てる力」は、好奇心のスイッチで育つ
よく「好奇心を持て」と言われますが、何に興味を持てばいいのかわからない…というのが正直なところではないでしょうか。
でも実は、「問い」はちょっとした違和感や、ちょっとした驚きの中から生まれます。
ある日、スーパーで売っているお弁当を何気なく見ていたときのこと。
「同じ唐揚げ弁当なのに、なぜかこっちは100円高い。何が違うんだろう?」
…そんな疑問から調べてみたら、使っている鶏肉の産地や味付け、さらには“売る場所によって値段を変える”戦略まで出てきて、すっかり夢中になってしまったんです。
これって、最初の「なんでだろう?」がなければ絶対に調べていなかったはずなんですよね。
小さな問いは、日常に落ちている
「面白がる力」は、特別なイベントやすごい体験から生まれるとは限りません。
むしろ、日常の当たり前の中にこそ、たくさんの“問いのタネ”が転がっています。
たとえば——
- コンビニの棚って、なぜ飲み物の陳列順が店舗によって違うのか?
- なぜ朝の満員電車では、あんなに全員スマホを見てるのか?
- 子どもはなぜ何度も同じ絵本を読みたがるのか?
これらは、ちょっと立ち止まって考えるだけで、「面白いテーマ」に変わっていきます。
「問いを育てる」ための、3つの習慣
じゃあ、どうやったらその“違和感”や“なんで?”に気づけるようになるの?という方のために、僕が個人的にやっている習慣を紹介します。
- 毎日ひとつ「なんでだろう?」を書き留める
寝る前にスマホのメモ帳にひとつ、「今日の問い」を残すだけでも効果アリです。 - ググる前に、まず自分の仮説を立ててみる
「たぶんこうじゃないかな?」と考えてから調べると、記憶にも残りやすいです。 - 人に話してみる
問いを誰かに話すと、自分の考えが整理されて、さらに新しい疑問が湧いてきます。
というわけで(続き)
問いを立てる力や面白がる力は、天才だけの特権じゃありません。
むしろ、ちょっとした“なんで?”を拾ってあげるだけで、誰でも育てていけるものです。
「自分には好奇心なんてないなあ…」と思っているあなた。
実はその言葉の裏に、「まだ見つけていないだけ」の面白さが隠れているかもしれません。
ゆっくりでいいので、今日の「なんで?」をひとつ拾ってみませんか?



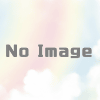

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません